【RFP(提案依頼書)作成・テンプレートサンプル(Word)あり】サイトリニューアルコンペを成功へ導く完全ガイド
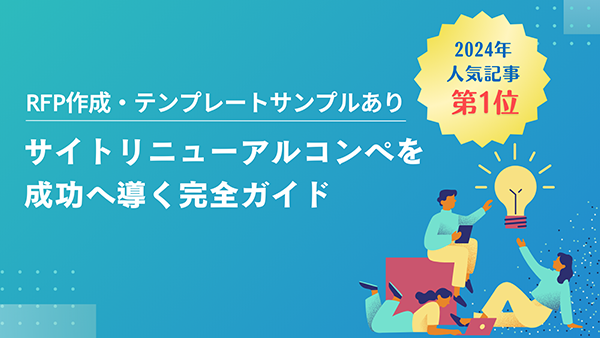
Blog東京・大阪のWeb制作会社アリウープのナレッジBlog

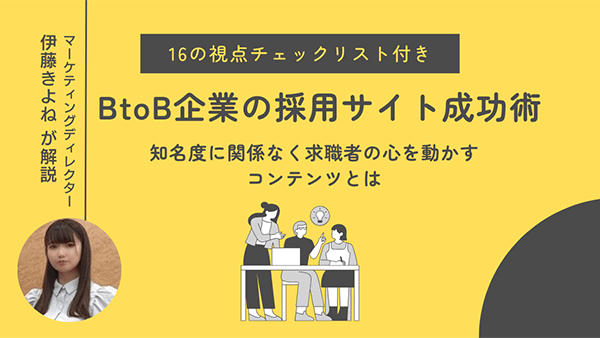
BtoBの事業を展開する企業にとって、採用活動は年々難しさを増しています。その理由のひとつが、BtoC企業と比べて一般的な知名度が低く、学生や若手人材との接点が持ちづらいことです。
例えば、就職活動中の学生にとって、「社名を知っているかどうか」や「自分の生活との関係性」が志望度に大きな影響を与えることは少なくありません。どれだけ安定した経営をしていても、社会的意義があっても、認知がなければ応募にすら至らないのです。だからこそ、企業自らが自社の魅力や働きがいを「直接伝える」採用サイトの設計が重要です。
本記事では、BtoB企業が採用サイトでどのような情報を発信すれば求職者の興味関心を引き出せるのか、そして応募・マッチングにつなげるための戦略的なコンテンツ設計のポイントについて、順を追って解説します。
改めて、BtoB企業の採用活動が抱える特有の課題を整理しましょう。
知名度が低く、最初から選択肢に入らない
多くの学生にとって、BtoB企業は「社名を聞いたことがない」「何をしている会社かわからない」存在です。そのため、たとえ業界内では優良企業であっても、ナビサイトで目に留まらず、説明会にも来てもらえないといった状況が生まれてしまうのです。
業務内容が抽象的に見えやすい
BtoB企業の業務は、クライアントの課題解決や専門的な技術支援、業務効率化の支援など、目に見える商品を持たないケースも多いため、仕事内容が学生にとって具体的にイメージしづらい傾向があります。
キャリアパスや成長イメージが伝わりにくい
「どんなふうに成長できるのか」「自分にどんな未来が描けるのか」が見えにくいのも、BtoB企業の課題の一つ。BtoC企業であれば“商品企画”や“サービス運営”などが具体的なイメージを喚起しますが、BtoBでは抽象的な職種名も多く、将来像を結びつけにくくなりがちです。
反対に、「知っているから応募した」という理由が通じるのがBtoC企業です。
CMやSNSでよく見かける企業は、それだけで安心感を与えられます。
BtoB企業の採用活動は、「まず知ってもらうこと」から始まるということですね。
BtoB企業の採用サイトでは、以下のような“情報の補完”が特に重要です。
▶「自社の事業内容をかみ砕いて伝える」必要がある
業界外の人が読んでも理解できるように、難しい技術用語や事業説明を避けて、身近な例・ストーリーで解説することが重要です。
例:「自動車のハンドル部品を開発している」といった場合でも、「実は、トヨタ車や日産車の操作性に貢献している会社」など、成果が生活にどうつながっているかを示すと学生が理解しやすくなります。
企業の規模感・直近の取り組みを載せることも効果的です。
▶「仕事内容と仕事の面白さ」を言語化する努力が必要
学生は「営業」「技術職」と言われても、日々どんな仕事をしているのかが想像できません。1日の仕事の流れ、実際のプロジェクト、やりがいを社員のストーリーで伝えることがカギになります。
▶「なぜこの会社で働く意味があるのか」を伝える
BtoB企業では、仕事の社会的意義や業界内の重要な役割が見えにくくなりがちです。
だからこそ、採用サイトでは「自社が世の中の裏側を支えている」ということを、具体的かつ感情に訴える形で伝えることが必要です。
このように、BtoB企業は「わかりづらさ」と戦う必要があるのです。
BtoB企業は、BtoC企業のような有名人を起用した派手な広告やブランド力で学生を惹きつけることはなかなかできません。その代わり、中身の濃い情報発信・仕事の本質への共感・職場のリアルな魅力を伝えることで、「志望理由の深さ」「マッチ度の高い応募者」と出会える可能性が高くなります。
採用サイトは、単に情報を並べるだけでは成果につながりません。どんな人に、どんな印象を持ってもらいたいのかを明確にしたうえで、発信の軸となる考え方を整理しておくことが大切です。とくにBtoB企業の場合は、自社らしさや仕事の価値を正しく伝えるために、以下のような視点を持って設計に臨むことが重要です。
▶自社が求める人材を明確化する
採用におけるミスマッチを避けるには、まず「どんな人物に入社してもらいたいのか」を明確にしておく必要があります。仕事の特性や会社の風土に合った人材像を、スキル・価値観・働き方の志向性などの観点から整理しましょう。
▶ペルソナを設計する
求める人物像が見えてきたら、その人物をひとりの“仮想の個人”として具体的に描いてみましょう。たとえば、「関東の私立大学で経済学を学ぶ3年生。成長意欲が高く、地元に貢献できる企業で働きたいと思っている」など、年齢・属性・考え方まで踏み込んで設計することで、より共感されるメッセージ発信が可能になります。
▶5W1Hで伝えるべきことを整理する
“誰に・何を・なぜ・いつ・どこで・どうやって”を軸に、採用コンテンツ全体を設計しましょう。これはページ単位の設計にも有効です。
これらの要素をしっかり考慮することで、単なる会社紹介ではなく、読み手にとって意味あるストーリーになり、正しくサイト設計をしていけるのです。
では、基本的な設計要素とは何か?を見ていきましょう。
① 情報設計
目的:ユーザーが必要な情報に迷わずたどり着けるようにする
主な内容:ページ構成、導線設計、ナビゲーション、各コンテンツの配置順
ポイント:求職者の不安や疑問を想定し、答えとなる情報を適切な順番で配置する
② コンテンツ設計
目的:どんな情報を、どの深さで、どの表現方法で伝えるかを決める
主な内容:社員インタビュー、FAQ、職種紹介、ビジョン、制度紹介など
ポイント:ペルソナに合わせて「何を伝えるか」より「どう伝えるか」がカギ
③ ペルソナ設計
目的:誰に向けてサイトを作るのか明確にする
主な内容:ターゲット像の設定(年齢、性格、価値観、情報行動など)
ポイント:“全員に刺さる”は“誰にも刺さらない”に等しい
④ 動線設計
目的:求職者の行動をスムーズにゴール(応募・説明会予約)に導く
主な内容:CTAボタンの配置、応募導線のわかりやすさ、LPとの連携
ポイント:行動の“詰まりポイント”をつくらない工夫が重要
⑤ 表現・ビジュアル設計
目的:感情に訴え、信頼や共感を生む
主な内容:写真・動画・カラー設計・UIトーン・イラストの活用など
ポイント:企業らしさとターゲット親和性のバランスを意識する
⑥ SEO設計
目的:検索エンジン経由で採用サイトに自然流入(オーガニック流入)を増やす
主な内容:キーワード選定、メタ情報の整備(メタ情報とは、ある情報そのものを説明するための補助的な情報のことです。たとえば「記事のタイトル」「作成日時」「著者名」など、内容以外の属性を指します)、URL構造の最適化、見出し階層の整理、構造化データの活用など
ポイント:
求職者が実際に検索するワード(例:「企業名+評判」「業界名+新卒採用」など)を意識して、自然にコンテンツ内へ反映
このように、多面的な設計がそろってはじめて、採用サイトは「ただの情報ページ」から「共感と行動を生むサイト」に進化します。順番に整理していきましょう。
もう一つ重要なことがあります。それは採用サイト制作を進める前に、必ず「戦略の整理」とともに、「関係者間の共通認識形成」を行うことです。
これを省略すると、制作過程で目的がぶれてしまい、成果につながらないサイトになってしまう可能性があります。
では、採用サイト制作にはどのようなことを意識して進行したらよいのか見ていきましょう。
社内ワークショップの実施:部署横断で集まり、企業の強みや伝えたい人物像をディスカッションします。採用サイト制作のメイン部署だけでなく、他部署の意見もしっかりヒアリングしましょう。
求職者インサイトの調査:既存社員インタビューや退職者アンケート、ペルソナワークで精度を高めることができます。
競合・他社分析:自社と類似業界の採用サイトを分析し、差別化要素や未開拓の魅力を見つけましょう。
経営層・上位者の確認:社長や役員など最終的な意思決定者を早い段階で巻き込み、方向性の齟齬を防ぎ、関係部署を円滑に進める体制を整えます。
制作会社との連携視点:UI/UXだけでなく、採用コンセプト・SEO・マーケ施策を一気通貫で相談できるパートナー選定が重要です。
成功するサイトの背景には、緻密な戦略整理と社内の共通認識形成があります。
プロジェクトをスムーズに進行させるためにも情報整理を行い、共通認識形成を意識してスタートしましょう。
次に、設計時の注意点を理解していきましょう。
①自社の「価値」をコンテンツでどう伝えるか?
どんな企業にも、他社にはない魅力や強みがあるはずです。採用サイトでは、それを読み手が“自分ごと化”できるように伝える必要があります。
競争優位性を明確にしよう
業界でのポジション、独自の技術、顧客との信頼関係、社員定着率など、数字や実績で伝えられる強みは、積極的にアピールしましょう。「大企業ではないけれど、この会社にはこの分野で圧倒的な強さがある」と伝われば、学生の評価は確実に変わります。
求職者が感情移入できる発信を心がけよう
単なる「強みの列挙」ではなく、働く人の想い・やりがい・エピソードといった感情に訴える情報を組み合わせることで、企業と求職者との距離は縮まります。文章だけでなく、動画や写真といったビジュアルコンテンツも効果的です。
②写真やデザインの力を軽視しない
求職者との心理的距離を縮めるうえで、親しみやすさを演出するデザインも重要な要素です。堅い印象を持たれがちなBtoB企業においては、サイト全体にユニークなネーミングを取り入れたり、可愛らしいキャラクターやイラストを活用したりすることで、柔らかい雰囲気や人間味を感じさせることができます。こうしたデザインは、求職者が「気軽に応募してもいいかも」と思える心理的な入り口をつくる効果があり、エンゲージメント向上にもつながります。
どれだけ中身のある文章を書いても、写真やデザインがチープであれば、ユーザーは「この企業は本気じゃないのかも」と感じてしまいます。
社内や社員の“リアルな雰囲気”を伝える写真を使おう
プロカメラマンによる撮影を検討し、社員の表情・働く姿・チームの雰囲気を丁寧に映し出しましょう。自然な笑顔や活発なコミュニケーションの様子が伝われば、求職者の「ここで働く自分」を想像しやすくなります。
また、多様な社員に登場してもらうことはとても良いことです。
ジェンダー、年齢、職種のバランスをとり、ダイバーシティに共感できる構成を意識しましょう。
“テンプレ感”のあるデザインは避けよう
他社と同じようなレイアウトやアイコンでは、印象に残りにくくなります。会社のカルチャーや業種に合った色づかいやフォント、余白の使い方まで配慮し、企業ブランディングの一部として採用サイトを構築することが重要です。
※~ビジュアルと動画コンテンツの効果的活用とAIについて~
ここで少しAIについても触れておきます。近年、画像や動画の制作にAIを活用する動きも増えています。確かに、AI画像生成を使えばコストを抑えつつ、ビジュアルを短期間で用意することも可能です。しかし、採用サイトにおけるAIビジュアルの利用には慎重さが必要です。
■“本物感”の欠如は、すぐに見抜かれる
特にZ世代は、「リアルかどうか」に非常に敏感です。AIで作られた“いかにも作られた笑顔”や“違和感のあるイラスト”は、逆に不信感を与えてしまうことがあります。特に「社員紹介」「オフィスの雰囲気紹介」といった場面では、実際の社員や職場の写真・動画を用いることで、信頼感を醸成できます。
AIだけに頼ると、企業独自の雰囲気や温かみが失われ、印象に残りにくくなる可能性がでてきてしまうのです。
AIを全て否定する必要はありませんが、求職者の共感や信頼を得るには“リアルさ”が必要であり、AI画像はあくまで補助的な手段にとどめるのが理想です。本物の社員・本物の職場・本音の言葉を映し出すことこそが、応募者の心に響く採用サイトをつくる鍵となります。取り入れる場合は慎重に行いましょう。
③採用は「全社で取り組むもの」という意識を
「関係者間の共通認識形成」について先ほど触れましたが、採用サイトは、人事部だけが関わればいいというものではありません。現場の社員や経営層が一体となって取り組むことで、初めて“本物の魅力”を伝えられるのです。
現場の声を積極的にコンテンツ化しよう
採用サイトでは、人事目線だけでなく、現場社員の声やストーリーも丁寧に拾いましょう。営業職や技術職、間接部門など、さまざまな部署の社員が「日常の仕事」「成長の実感」「チームとの関係性」を語ることで、職場の多様な魅力が伝わります。
経営層のメッセージで「本気度」を伝える
代表メッセージや経営層のインタビューも効果的です。会社の未来像や、若手への期待を語るコンテンツを設けることで、求職者に「この企業は人を大事にしている」という印象を与えることができます。
④採用サイトは「つくって終わり」ではない
最後に忘れてはならないのが、採用サイトは“完成して終わり”ではなく、運用し続けることで価値を発揮するメディアであるということです。
定期的な情報更新が信頼感につながる
新入社員の紹介、内定者の声、最新プロジェクトの紹介など、定期的に記事や動画を追加していくことで、「企業としての活気」や「成長」を感じ取ってもらいやすくなります。
noteやSNSと連動させ、情報発信を続けよう
社外向け広報で活用しているnoteやSNSがあるなら、それらと採用サイトを連動させるのが有効です。「この会社は日々の活動をきちんと発信している」という安心感が、エントリーの後押しになります。特にSNSは、社員の日常やイベント風景、働く場の空気感をリアルタイムに伝えられるため、応募前の「もっと知りたい」を後押しする力を持っています。つまり採用サイトとSNSは切り離すのではなく、行動導線上で互いを補完し合う存在として設計することが重要です。
ここまで見てきたように、BtoB企業が採用活動で成果を出すには、「知られていない企業だからこそ伝える工夫」が必要です。
”どんな写真を使い、どんな社員に語ってもらい、どの順番で何を届けるか”
その一つひとつが、応募者の印象や行動に大きく影響します。
つまり、採用サイトは「見た目」や「掲載内容」だけではなく、「どう伝えるか」の“設計力”が鍵になります。
特にBtoB企業では、単なる情報発信ではなく、”相手の理解や感情を動かす情報設計や感情設計”が必要不可欠です。
では、実際にその設計をより高めていくために、どのような視点や問いを持てばよいのでしょうか?
次の章では、学生に選ばれる採用サイトにするポイントをお伝えしていきます。
求職者は「自分ごと」として職場を想像できる情報を求めています。
以下のような情報が整理されていることが、応募数や面接辞退率に大きな影響を与えますので、まずこれらの基本的な項目は必ず掲載するようにしましょう。
例えば、今はほとんどの企業が掲載している”社員インタビュー””社員の一日”というコンテンツ1つにしても、作成ポイントがあります。あくまで一例ですが見ていきましょう。
※こちらの例は中途採用にも当てはまる内容も多くありますが、学生(新卒、第二新卒、若手の求職者)を主にターゲットとした内容で解説いたします。
1. 学生目線でのリアルなストーリー設計や見せ方
●先輩社員インタビュー
単なる職歴紹介にとどまらず、「学生時代に取り組んでいたことがどう仕事に活きているか」「就活中に感じた不安や迷い」「入社後にギャップを感じた点」など、感情や思考のプロセスを含めて発信することで、学生との心理的距離が一気に縮まります。
⇒「1日のセルフドキュメンタリー形式」
社員自身にスマホで「出社〜ランチ〜退勤」までの一日を短く撮影してもらい、それを編集して公開。学生が実際の働き方や雰囲気を体感でき、インタビューよりもリアルで没入感があります。
⇒「入社後○ヶ月のリアル」シリーズ
内定者や新入社員が、自分の成長や戸惑いを日記・Vlog形式で発信。過去の振り返りではなく「進行形のストーリー」だからこそ共感を呼びやすいです。
⇒「同期座談会・クロストーク」
1人の社員紹介にとどまらず、複数人で“本音トーク”をしてもらう形式。学生が気になる「ぶっちゃけ残業ある?」「失敗したことある?」などを語ると親近感が高まります。
上記のように、学生がSNSや動画文化に慣れた世代であることを前提に、よりリアルに感じてもらえるような内容も検討してみましょう。
2. キャリアパス・成長の道筋を示す
●10年後にどうなれるのか?が見える構成に
人材育成方針や資格取得補助制度、OJTなど、具体的な育成・研修制度に関する情報もしっかり記載する必要があります。これらも個人の成長を重視する求職者にとって非常に知りたい情報です。
若手→中堅→管理職へのキャリアステップを図やストーリー形式で掲載し、「この会社で成長したらどんな未来があるのか」を可視化することが重要です。
また、ジョブローテーション制度や異動事例などが紹介されていれば、「長く働けそう」「飽きずに成長できそう」と感じてもらいやすくなります。
3. “やりがい”よりも“共感”で惹きつける
●ミッション・バリューを等身大の言葉で語る
自社の存在意義や大切にしている考え方を、難しい表現や抽象的な理念ではなく、社員のエピソードや日々の行動から伝えることで、より学生の心に刺さります。
●仕事の社会的インパクトの伝達
BtoB企業の場合、普段目に見えにくい商材でも、「この会社の製品が、◯◯業界を支えている」「◯◯を効率化し、人々の生活を支えている」といったストーリーに落とし込むことで、“世の中の一部を動かしている”実感を持たせられます。
4. 学生の不安を解消する“信頼”の情報設計
●よくある質問(FAQ)の設置
「ノルマはある?」「激務?」「配属先は選べる?」など、学生が気になるけど聞きづらいことにあらかじめオープンに回答しておくことで、企業への信頼感を高め、応募の心理的ハードルを下げられます。
求職者が質問しづらい内容についても、あらかじめオープンに回答しておくことが重要です。このような透明性の高い発信は、企業の誠実な姿勢やオープンマインドな社風を伝えると同時に、応募への心理的ハードルを下げ、ミスマッチの防止や内定辞退率の低下にもつながります。
●福利厚生・働く環境も重要ポイント
福利厚生の見せ方も学生の心をつかむ重要な要素です。たとえば月1回の社内カフェランチや、旅行手当を活用して仲間と海外へ行ける制度、最新ガジェット購入を会社が補助する仕組みなど、日常をちょっと楽しくする工夫は強い関心を集めます。
また近年では、集中力を高めるための個室型ワークブース、雑談やアイデア出しの場として使われるカフェスペース風の休憩エリア、社内の交流を促進するフリースペースなど、オフィス設計そのものが企業文化を語るコンテンツとなっています。これらの設備は、企業の価値観(効率性/自由度/働きやすさ)を象徴的に伝える要素として、積極的に写真や紹介文で掲載することが重要です。
こうした「働く+楽しむ」福利厚生をストーリーに織り交ぜて紹介することで、自社らしい魅力が際立ちます。
●入社後のサポート体制
教育制度やフォローアップ体制、メンター制度など、入社後の安心材料を明示することで、「不安だけどここなら挑戦できそう」と感じてもらえます。
5. 親しみやすさを演出するデザイン工夫
●柔らかいトーンやユニークな表現
「堅い会社」「おじさんばかり」というBtoB企業の先入観を払拭するために、親しみやすいキャラクター、イラスト、ネーミングなどを活用するのも効果的です。コンテンツにユーモアを交えることで、堅実さと柔軟さのバランスを感じさせられます。
知名度が低いBtoB企業でも、学生が「この会社、なんか気になる」と思う瞬間をつくることは可能です!
心を動かすポイントは、「自分に関係ありそう」「働いている自分をイメージできる」「信頼できそう」と思ってもらえるかどうかです。
採用サイトに必要な設計要素については先ほどお伝えしましたが、求職者の心を動かし、行動へと導くためには、“情報設計”から“感情設計”へと進化する必要があります。
ここでは、採用活動をさらに強化するために自問すべき「16の視点」を紹介します。
自社の採用サイトはどうか?是非確認してみてください。
※今回は主に学生、新卒、若手求職者をターゲットとした視点としております
→「○○に強い人」「真面目な人」といった表層的な分類ではなく、
“人としてどんな物語を歩んできた人なのか”まで想像し、
サイトの語り方・導線・写真表現に反映させていくことが必要です。
→差があっても、伝わらなければ意味がありません。
自社の独自性が、学生の文脈で届くように“翻訳”する視点を持つようにしましょう。
→ 応募までの“行動導線”は採用サイト単体では完結しません。説明会・SNS・口コミ・OB訪問など、前後の接点との連動設計が重要です。
採用サイトは信頼性や詳細情報を提供する場であり、一方SNSは“ファーストタッチ”や“比較検討中の共感材料”として大きな役割を担います。
→「先輩の声」はどこにでもあります。
差を生むのは、どんな体験を通してその言葉が生まれたかを丁寧に描けているかどうかです。
→リリース後こそが本番です。
数字と人の声の両面で改善サイクルを回せる体制づくりが成果につながります。
→採用戦略は、「何人集めるか」より「誰に刺すか」です。
その明確さがあってはじめて、サイトに込めるべき言葉・構成・ビジュアルが決まります。
自社採用サイトのチェックはできましたか?
採用サイトは、企業の姿勢そのものを映す鏡です。
本気で取り組むほどに、きっと“本気の人材”が集まってくるはずです。
BtoB企業の採用活動では、知名度や派手さで勝負することは難しいかもしれません。
だからこそ、どんな順序で、どんな言葉で、誰の声で、何を届けるか
――その「設計力」こそが成果を左右します。
事実を整理して届ける「情報設計」と、心を動かす「感情設計」の両輪で制作していくようにしましょう。
もし、採用サイト制作で”このままでよいのか?”不安があるなら、採用ブランディングや情報設計に強い制作会社に相談するのも有効です。
「自社に合った採用サイトのかたちがわからない」「どこから手をつければいいかわからず悩んでいる」といった場合でもご安心ください。
アリウープは戦略設計からコンテンツ企画、デザイン・運用まで一貫してサポート可能です。
まずはお気軽にご相談くださいね!
学生のニーズや重視するポイントをもとにコンテンツ改修。細部まで魅力が伝わる新卒採用サイトへ コベルコシステム株式会社様
▶バランスを重視し細部までこだわったコンテンツ追加が功を奏し、サイト改修後の効果測定では採用サイト全体の平均セッション時間が5分以上となり、離脱率・直帰率についても一般的な基準と言われている40%よりもかなり良い数値となっていました。