【RFP(提案依頼書)作成・テンプレートサンプル(Word)あり】サイトリニューアルコンペを成功へ導く完全ガイド
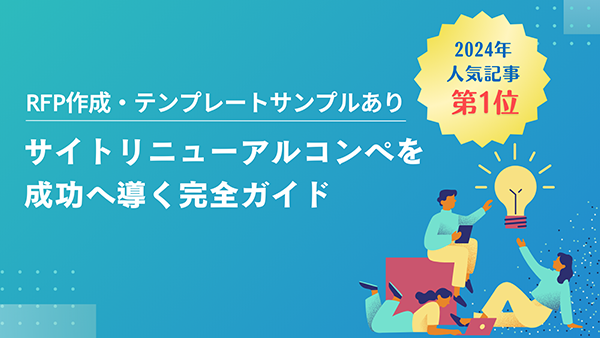
Blog東京・大阪のWeb制作会社アリウープのナレッジBlog

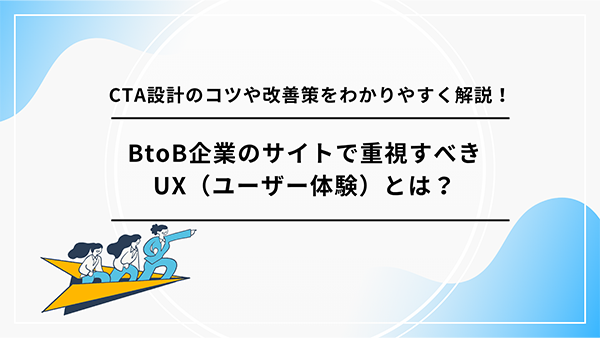
BtoBサイトのリニューアルや新規構築を考えるとき、「とりあえず情報が載っていればいい」「デザインはかっこよくしておけばよい」と思っていませんか?しかし、それではせっかくの見込み顧客を取りこぼしてしまう可能性があります。
BtoBサイトにおけるユーザー体験(UX)は、単なる“見た目の良さ”ではありません。情報の探しやすさ、導線の分かりやすさ、信頼感を与える設計など、成果に直結する要素です。また、実際にUXの質が「問い合わせ数」や「営業効率」に大きく影響していることをご存知でしょうか?
この記事では、BtoBサイトにおけるUXの重要性と具体的な改善ポイントを、実際の成功事例を交えて分かりやすく解説していきます!
BtoBサイトの改善やリニューアルを考えるときによく出てくる言葉が「UX」と「UI」。
似たように扱われがちですが、この2つには明確な違いがあります。
簡単にいうと
UI(ユーザーインターフェース)は「見た目」や「操作する画面そのもの」
UX(ユーザーエクスペリエンス)は「その画面を通じて得られる体験」
です。
例えばUXは迷わず情報にたどり着けるか、信頼感が持てるか、行動に移しやすいかといった“全体の流れ”を意味します。
言い換えるなら、UIはUXの一部であり、UXを良くするためにUIをどう設計するかが鍵になるのです。
BtoC(個人向け)サイトでは、感情的な訴求やビジュアル重視が多いですが、BtoBサイトではそれとは異なります。BtoBでは、企業の担当者が複数人で検討・決裁を行うため、情報の正確さ・信頼性・論理性が重視されます。
BtoBにおけるUXとは、以下のような体験を指します
UXは「ストレスなく判断できる体験」を設計することです。特にBtoBでは「購入までの検討期間が長い」「関係者が多い」という特性を理解したUXが求められます。また、かつてはBtoBサイトにおけるスマートフォンの閲覧割合は少なかったですが、近年は増加傾向にあります。
※Call To Action(コール トゥ アクション)の略で、お問い合わせやホワイトペーパーダウンロードなどの行動を促す”行動喚起”を意味します
改めてUIとUXの違いについてBtoBサイト制作の視点から理解しましょう。
■ UIは“見た目”、UXは“体験”
BtoBサイトでは「UIが整っていればよい」と誤解されがちですが、UIが良くてもUXが悪ければ成果にはつながりません。どちらも重要なのです。
■ BtoBサイトでの違いを整理すると
| 観点 | UI(見た目) | UX(体験) |
| 定義 | ユーザーが触れる視覚・操作部分の設計 | サイトを通じて得られる体験全体の設計 |
| 例 | 配色/フォント/レイアウト/ボタン | 情報設計/導線設計/CV率改善/問い合わせまでの流れ |
| 評価指標 | 見やすさ・使いやすさ・美しさ | ストレスのなさ・迷わなさ・問い合わせ完了率 |
| 担当者 | デザイナー | UX設計者・マーケター・IA(情報設計者) |
基本的には上記のイメージとなります。
「サイトをカッコよく、新しい感じのデザインで作ったのに、なぜか問い合わせが増えない」
というご相談をうけることがあります。
その原因の多くは、「見た目(UI)から設計を始めてしまった」ことにあります。
BtoBサイトで成果を出すには、“ユーザー体験(UX)”を先に考え、それに合わせて見た目(UI)を整えることがとても重要です。
BtoBサイトに訪れるユーザーは、何かしらの課題や目的を持っています。
たとえば以下のようなケースが考えられます。
例:情報システム部の担当者の場合
状況: 新しい業務システムの導入を検討している
行動: 複数のベンダーサイトを比較し、スペックや価格、セキュリティの詳細を確認する
求めている情報: スペック表、運用コスト、サポート体制、セキュリティ対応状況
例: マーケティング担当者の場合
状況: 自社の商品PRのために、支援してくれる制作会社を探している
行動: 制作実績やマーケティング支援のノウハウがある会社を調べる
求めている情報: 実績(特に自社と同じ業種)、コンテンツ企画の事例、相談できる窓口の有無
このようにユーザーは、まず情報を集め、比較し、検討し、社内で相談し、ようやく問い合わせに進むという段階を踏んでいきます。
決裁者の場合だと、
例: 経営層・決裁者の場合
状況: 担当者から提案されたベンダーが信頼できるか最終判断したい
行動: 自らサイトにアクセスし、理念・沿革・導入実績などを確認する
求めている情報: 会社概要、取引実績、代表者メッセージ、導入効果の信頼性
と、また行動や求める情報が違うこともあります。
このように、ユーザーごとに「訪問目的」や「知りたい情報」が大きく異なります。
BtoBサイトでは「訪問者が迷わず、目的の情報にたどり着けるか?」を設計の起点にしましょう。
UX設計とは、上記のような訪問者の行動を想定し、
といった視点で、「サイト内での体験の流れ」を設計することです。
UXがしっかり設計されたら、その流れをスムーズに感じてもらうために
といった“UI(見た目)”を整えていきます。
つまり、UXが「地図」で、UIが「案内板」のような関係です。
見た目から考えると、こんな失敗が起きがちです。
これでは、せっかく時間や費用をかけて制作しても、ビジネス成果にはつながりません。
UXを先に考えることで、
といった工夫がしやすくなり、ユーザーの「検討〜問い合わせ」までを自然に導けます。
UX視点で設計すると、
と、整理できます。
UIはその体験を支えるための「表現手段」であり、UXこそが設計の出発点なのです。
上記のことから、美しいUIも大切ですが、BtoBサイトでは「問い合わせしたくなる体験設計(UX)」が最優先ということになりますね。
UXが設計できていれば、UIは“伝わる形”に落とし込むだけ。
逆に、UXのないUIは“見栄えがいいだけの箱”になってしまうのです。
UI、UXの違いを理解できたところで、ここからはUXについてもう少し深く学んでいきましょう。
UX(ユーザーエクスペリエンス)は直訳すれば「利用者の体験」です。BtoCのようなエンタメ的な体験とは異なり、BtoBにおけるUXは以下の3つの視点で捉えると理解しやすくなります。
● 「迷わない」情報設計ができているか
「どこに何があるのか」「どのページを見れば目的を果たせるか」が一目でわかること。たとえば、導線が明確なグローバルナビゲーションや、トップページからの視線誘導設計などです。
● 「信頼できる」コンテンツがあるか
実績・導入事例・メンバー紹介などがしっかり掲載されていること。信頼性を可視化することで、商談前に心理的なハードルを下げます。
● 「行動しやすい」設計になっているか
資料請求、問い合わせ、ホワイトペーパーダウンロードなど、“次のアクション”が明確に設定されている状態です。
BtoB UXの三大要素
[迷わない導線] → [信頼される情報] → [行動を促すCTA] = コンバージョンへ
とつながります。
ではUXを改善することで、どのような成果が期待できるでしょうか。
一例を見てみましょう。
成果1:問い合わせ率の向上
情報がスムーズに伝わることで、訪問者が「これは相談してみたい」と思いやすくなるのです。
情報が整理され、サービスの魅力が伝わりやすくなることで、問い合わせや資料請求が増加します。
▶︎ 例:CTAの位置をファーストビューに置いた結果、問い合わせが倍に増加
成果2:滞在時間・離脱率の改善
“自分に必要な情報がある”と感じてもらえると、ユーザーはサイト内を回遊します。滞在時間が長い=信頼度アップのサインです。また、「このサイトはわかりやすい」と思わせる設計にすることで、訪問者がページ内をしっかり読み込むようになり、SEO評価にもつながります。
▶︎ 例:サイト制作事例に関して業界別ページを作成→関連事例ページへの遷移率がアップ
成果3:営業活動の効率化
UX改善で、ユーザーが自己解決できる範囲が広がれば、初回商談の質が上がり、営業側の説明工数も減ります。サイト上でサービス紹介・事例・よくある質問などを的確に提示することで、営業がゼロから説明する必要が減り、効率的な営業活動が可能になるのです。
▶︎ 例:よくある質問ページを強化→問い合わせ前の疑問を解消し、リードの質がよくなったり、案件化率向上
このように様々な効果が期待できます。
次はよくある課題と改善策例を見てみましょう。
● 情報が複雑すぎる
→ 情報設計を見直し、1ページ1テーマで伝えるようにする。図解や表の活用も有効です。
改善策:情報設計を見直し、1ページ1テーマで伝える。図解や表を使って構造を可視化しましょう。
● CTAが不明確/複数ある
→ できればページごとに1つの明確な行動を促すCTAに絞り、視認性高く配置。
改善策:「このページでしてほしい行動」を明確にし、1ページ1CTAに絞りましょう。例えば「資料請求」「無料相談」のボタンを主要導線のみに配置。ページ構成をシンプルに。「1ページ1テーマ」を徹底し、図表やイラストで視覚的に伝えるようにしましょう。
● モバイル対応が不十分
→ レスポンシブ対応はもちろん、読み込み速度の最適化や、タップ操作しやすいUIに調整しましょう。
改善策:PC前提の設計だけでは今のBtoBには通用しません。スマホでも「迷わない・押しやすい」を意識する必要があります。
● 実績や事例が探しにくい
→ 業界別・課題別などでフィルター検索できる導線設計をすると、訪問者の信頼獲得に効果的です。
改善策:業界・業種・課題別でフィルタリングできる設計にし、信頼感と導線の明快さを両立しましょう。
複雑だったサービスページをカテゴリ別に分け、導線を明確化。CTAボタンの配置も最適化したことで、問い合わせ件数が倍増。
UX改善後にマーケティングオートメーション(MA)を導入。閲覧ページ履歴に基づいて営業がアプローチしやすくなり、案件化率が向上。
専門用語が多く伝わりづらかった製品ページを図入りでわかりやすく再構築。CTAを明確化し、問い合わせが倍増。
複数ペルソナに配慮した情報設計を行い、事例やデザインページの追加や検索性の向上・サイト内の回遊を増やす仕掛けも盛り込み問い合わせが2.2倍に。
問い合わせ完了までをいくつかのステップに分け、「問い合わせに至るまでに挫折しないサイト構造」に。企業イメージ向上のためのコンテンツについては、「ユーザーが持っている企業イメージ」と「企業として持たれたいイメージ」に生じている乖離を埋める施策を実施。顧客開拓につながるお問い合わせが増加しました。
逆に失敗事例としてよく話を聞くのが
「情報をたくさん載せたのに、なぜか問い合わせが減った」ということです。
その原因は“情報量”ではなく、“体験設計の不足”にあるのです。
ほかにもよく誤解されているのが
①「UI/UX改善するなら大規模になるでしょ?予算もリソースもないし・・・」
→ まずは既存ページの見直しからでも成果は出せます。
UX改善というと、大規模なリニューアルを思い浮かべがちですが、実は小さな改善の積み重ねでも効果は出ます。
たとえば以下のような方法です。
■アクセスが多いページの見出しや導線だけ整理する
→「何のページなのか」「次にどう行動すればいいか」がわかりやすくなり、離脱率が改善
■問い合わせボタンのラベルを「お問い合わせ」から「無料で相談する」に変更
→クリック率が倍に上がった企業事例も
■「よくある質問」ページをトップメニューからでも見られるように導線追加
→訪問者の自己解決率が上がり、営業問い合わせの質が向上
②「今までずっと同じ配置にしていたデザインを変えると逆にわかりづらくなるのでは?」
→ デザインとは“視覚による案内板”です。情報を整理すれば、むしろ判断しやすくなります。
「今のままが見慣れていて使いやすいのでは?」という不安はよく聞かれます。
しかし、BtoBサイトでは「誰が初見でも迷わない構造」が求められます。
たとえば以下のような方法です。
■製品説明ページの冒頭に「どんな課題に向いているか」箇条書きを追加
→ 読者が「自分ごと化」しやすくなり、滞在時間が伸びる
■お問い合わせページに、「こんな人にオススメ」と簡単な利用例を載せる
→フォーム離脱率が下がり、成約率アップにつながる
このように、BtoBサイトでは、こちらが伝えたい内容を盛りだくさんただ掲載すればいいのではありません。
”訪問者が情報をどう受け取り、どう判断するか=UX(ユーザー体験)”がカギを握ります。
リソースが限られているときほど、「何を足すか」ではなく「何を減らすか・整理するか」という視点が重要なのです。
一つの改善でも、ユーザーにとっての“迷い”が減れば、成果に直結しますよ!
では実際の改善の進め方を見ていきましょう。
「UX改善」と聞くと難しそうに思えるかもしれませんが、実際には段階を追って進めれば、確実に成果につながります。
とくにBtoBサイトでは、ユーザーの意思決定が慎重で段階的だからこそ、「サイトのどこで迷っているのか」「何が障壁になっているのか」を明らかにしながら改善を進めることが重要です。
また、UX改善は一度きりで終わるものではありません。運用と並行して定期的に見直すことで、“育てていくサイト”に変えていくことが可能です。
以下のような基本ステップに沿って、制作会社と一緒に進めていくと効果的です。
STEP1:ヒアリングと解析(現状把握)
まずは、現在のサイトにおける課題を「データ」と「関係者の声」の両面から洗い出すことがスタートです。
■GA4などで、どのページで離脱しているか?どの導線が機能していないか?を可視化・UI/UXの専門家によって定性的な観点でサイトの利便性を数値化するヒューリスティック評価を行う
■営業やカスタマーサポートなど、顧客と接している担当者から“リアルな困りごと”をヒアリング
このステップを飛ばすと、「見た目だけのリニューアル」で終わってしまいます。
STEP2:ペルソナとカスタマージャーニーの作成
どんなユーザーが、どんな課題を持ち、どう比較・検討していくのか
――その流れ(ジャーニー)を具体的に設計します。
■例)「情報システム担当者」「経営層」「現場マネージャー」などの複数ペルソナを設定
■それぞれがサイトに来る目的や導線・ゴールを整理し、「どこで何を伝えるべきか」を明確化
サイトの構成やCTA設計に大きく関わるため、UX設計では必須の工程です。
STEP3:サイトマップ・ワイヤーフレーム・デザインの作成
整理された情報をもとに、どのページに何を配置するかを設計していきます。
■サイトマップ:ステップ2をもとに、必要に応じてコンテンツの追加を検討します。
■ワイヤーフレーム:各ページの画面設計図を作成。カスタマージャーニーをもとに回遊性やユーザビリティを意識して設計します。
■デザイン:ワイヤーフレームをもとにデザインを作成し、テキストや画像・ボタンなどの仕様を決めていきます。
制作会社と共有しながら「見やすさ」「迷いにくさ」「導線の自然さ」を調整します。
この段階での設計ミスは、あとから修正が難しくなるため慎重にしていきましょう。
STEP4:ユーザーテストでの仮説検証
関係者や実際の想定ユーザーに触ってもらい「どこで迷うか」「目的は達成できるか」を検証します。
■例:「サービスページを見て、資料請求してもらう」までの流れを通してもらう
■「クリックされない」「途中で離脱する」などの課題を見つける
想定どおりに機能しているかどうかを、事前に確認できる貴重なフェーズです。
STEP5:リリース後の継続的な改善
サイトを公開して終わりではありません。
リリース後もアクセス解析やヒートマップなどを活用して、実際の動きを観察しながら調整していきます。
■CTAがクリックされているか?導線は意図どおり機能しているか?
■定期的に営業チームからフィードバックをもらい、更新内容に反映
実際のユーザーの行動を見ながら、仮説→検証→改善のサイクルをまわすことが、BtoBサイトにおけるUX成功のカギです。
これらを全て担当者一人で行うのは難しいので、信頼できる制作パートナーと一緒に取り組んでいくことをおすすめします。
そして、制作会社選びも重要だな…ということもご理解いただけたと思います。
前述しましたが特にBtoBサイトの場合は”企業イメージとあっている、かっこいいデザインが得意!デザイン重視です”という制作会社に依頼した場合、UI/UXやマーケティングの視点が抜けてしまい、結果的によいサイトにならない場合があります。
「マーケティング視点があるか」「改善提案が継続的にあるか」はパートナー選定時の重要ポイントです。
次は自社のサイトを簡易的にチェックしてみましょう。
チェック① 自社サイトのトップページ、5秒で何をしている会社か伝わる?
どう見直す?
■ファーストビューに「誰に」「何を」「どう解決する会社か」の要約が入っているか
例:「○○業界向け業務効率化ツールで、月100時間の作業削減を実現」
■メイン画像の下に、サービス内容をひと言で説明するテキストがあるか
例:「製造業向けの生産管理クラウド|すぐに導入、現場で使える」
なぜ重要?
→ BtoBの訪問者は忙しく、5秒で「違う」と思えば離脱します。自社の強みや対象顧客が一目で伝わることが重要です。
チェック② CTA(お問い合わせ・資料請求)は、目立つ場所に設置されている?
どう見直す?
■「資料請求はこちら」「お問い合わせ」はページの最上部または最後に1つだけ、色で目立たせる
■CTAボタンが複数ある場合、「まずどこを押せばいいかわからない」状態になっていないか確認する
■スマホでもCTAがスクロール中に常に表示されるなど、UXに配慮しているか見直す
なぜ重要?
→ CTAが複数あると迷いが生まれ、逆に離脱を招きます。BtoBの場合、1つの明確な行動導線がコンバージョンに直結します。
チェック③ 事例や実績は、「探しやすい場所」にある?
どう見直す?
■グローバルナビゲーションに「導入事例」や「お客様の声」などの項目があるか
■トップページから2クリック以内で主要事例にアクセスできるか
■業種・課題別などで事例を絞り込めるような構造になっているか(理想)
なぜ重要?
→ 多くのBtoBの訪問者は「自社と同じ業種・規模でも効果があるか?」を気にします。
導入事例を探すのに手間がかかると、それだけで離脱要因になります。
UX改善を進めても、CTA設計が弱いとコンバージョンにはつながりません。
BtoBサイトで成果を上げるには、「どのタイミングで、どんなCTAを、どこに置くか」まで設計することが不可欠です。
ただ目立たせるだけでは不十分で、「適切な行動を促す流れ(導線)」がなければ、せっかくの訪問者も離脱してしまいます。
①CTAは「行動の目的」に合わせて設計する
BtoBサイトでは、ユーザーの関心フェーズに応じて求める行動が異なります。
以下は一例です。
| ユーザーのフェーズ | 有効なCTAの例 | 設置箇所のポイント |
| まだ情報収集中(潜在層) | 「導入事例を見る」「資料をダウンロード」 | トップページ・サービス紹介ページの中間 |
| 興味を持った(比較検討中) | 「料金表を見る」「○○と他社比較」 | 機能紹介・プランページ |
| 導入を前提に検討中(顕在層) | 「無料相談」「お問い合わせ」 | 各ページの最下部、問い合わせページへの導線 |
「すぐに問い合わせてくる前提」で設計してしまうと、潜在層を取りこぼす恐れがあります。
”フェーズに応じた“段階的なCTA”を用意しておくのが理想です。
②CTAは「目立たせる」より「迷わせない」
ありがちな失敗に、「とにかく目立たせよう」としてCTAがページ内に乱立してしまうケースがあります。
③導線設計の具体的な工夫
CTAの“前”の体験も見落とさず、流れとして最適化することがポイントです。
BtoBのサイトでは、「とりあえずボタンを設置」ではほぼ成果につながりません。
ユーザーの心理や行動ステップに沿って、「次にどんな行動をとってもらうか」を明確に定めたCTAが必要です。
そのうえで、
この3点を意識して構築しましょう。
“温度感が高くない層”にもアプローチするために、資料ダウンロードやノウハウPDFなど、段階的なリード獲得の導線も検討しましょう。
■PageSpeed Insights(Google)【無料】
特徴: ページ表示速度を分析し、UX改善に活かせる
できること:
・モバイル/PCでの速度スコアを確認
・改善すべき箇所の提案(画像圧縮やJavaScriptの最適化など)
・コアウェブバイタルにも対応(UX指標として重要)
リンク:
https://pagespeed.web.dev/
■Google Analytics 4(GA4)【無料】
特徴: ユーザー行動の把握に欠かせない基本ツール
できること:
・ユーザーの経路、離脱ページ、滞在時間などを分析
・目標設定やコンバージョンの測定
・導線設計の見直しに使える
リンク:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
■MIERUCA(ミエルカ)ヒートマップ【一部無料】
特徴: SEOツールで有名な「ミエルカ」の無料ヒートマップ
できること:
・ページごとの熟読エリアの可視化
・ユーザーの離脱箇所の分析
・日本の会社なのでサポート体制も安心
参考リンク:
https://mieru-ca.com/heatmap/
まずは無料でできるものから取り入れてみましょう。
BtoBサイトにおいて、ただ見栄えのいいデザインや流行のUIを導入するだけでは成果にはつながりません。
大切なのは、訪問者が「迷わない」「信頼できる」「次のアクションに進める」
そんなユーザー体験(UX)を設計することです。
本記事でご紹介したポイントやチェックリストをもとに、今日からでも改善のヒントが見つかるはずです。
しかし、UXの設計や導線の見直しは、コンテンツの構成やビジネス戦略とも密接に関わるため、一人で取り組むには難しい部分もあります。
BtoBサイトは、会社の“営業資産”そのもの。 UI・UXを見直すことは、未来の成果につながる第一歩です。
小さな改善からでも、ぜひ着手してみてください。
「何から手をつければいいのか分からない」「やってみたけどうまくいかない」
そんなときは、UXに強い制作会社に相談するのが近道です。
自社では気づかなかった課題や改善の方向性を、プロの視点から見出すことができます。
サイト改善や運用でお悩みの方はぜひアリウープにご相談ください!