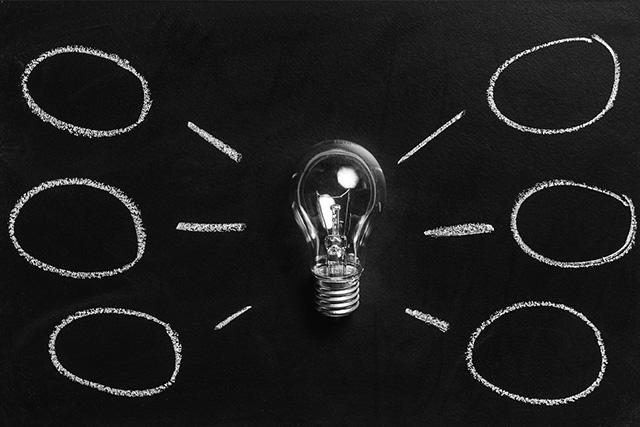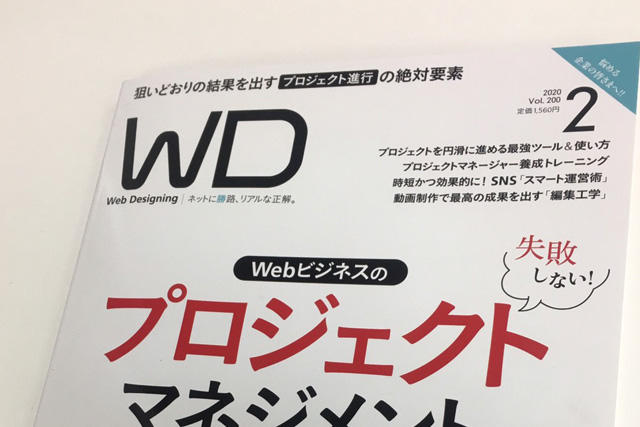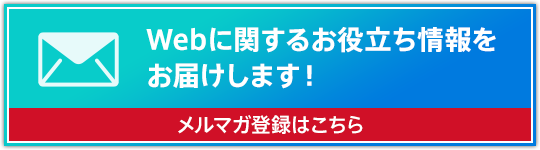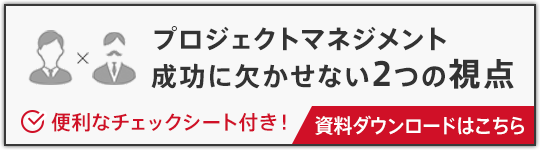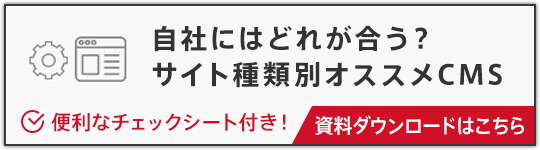Blog東京・大阪のWeb制作会社アリウープのナレッジBlog

【2024年最新版】初心者必見!アクセス解析、まずは何を見るべき?

Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを導入し、「さあ、毎日Webサイトのチェックをするぞ!」と意気込んでみたものの、「項目が多すぎてどの数値を見ればいいのかわからない!」「この数字は良いの?悪いの?」と感じてアクセス解析に挫折してしまったことがあるWeb担当者の方、多いのではないでしょうか。しかしWebマーケティングとアクセス解析は切っても切り離せないものです。ここを疎かにしてしまってはWebサイトの成果を確認することはできませんし、効果的な施策を生み出すことはできません。
そこで今回は、一度挫折してしまった方でも、初心者の方でも「アクセス解析をやってみよう」と感じていただけるように、「アクセス解析でまず見るべき項目」について解説をしていきます。
index
まずは「自社サイトの目的」を思い出そう
アクセス解析に及び腰になってしまうのは「どの項目をみればいいのかわからない」「データを集めてもその後のアクションがわからない」といった理由が多いのではないでしょうか。
そもそもアクセス解析は「自社サイトがどれだけ目的に近づけているか」あるいは「何がボトルネックとなって目的に近づけていないか」を明確にするためのものです。つまり、「解析」が先立つのではなく、あくまでも「目的」を優先すべきなのです。そのため、まずは自社サイトを通してどのような目的を達成したいかを思い出し、その目的を達成するためには何を知るべきかという観点に立つことから始める必要があるのです。
では次項から、主流な4つの目的と、それに合わせて見ていく項目について紹介していきます。
目的1:Webサイト上で商品・サービスの販促を行う場合
販促サイトやランディングページなど、商品やサービスの販売促進を目的としているサイトでは「コンバージョン数」が重要な指標となります。具体的には「お問い合わせ」や「資料請求」がどれだけの数なされたかです。
お問い合わせや資料請求をするユーザーは、それだけ商品・サービスに対する興味関心が高いことを意味していますので、販促という目的に近づけていると言えるでしょう。
目的2:商品や自社の認知向上を目的にする場合
商品・サービスの認知向上を目的としたサイトでは、言葉通り「多くの人にブランドを認知してもらう」ことを目指しています。そのため、「訪問者数」と「閲覧数(PV数や動画などの視聴数)」をまずチェックしていくべきでしょう。
これらの項目を見ることで、「どれだけのユーザーに情報が届いているか」を知ることができるので、ブランド認知にサイトがどれだけ寄与しているかを判断することができるのです。
目的3:コスト削減を目的にしている場合
「コスト削減を目的にしているサイト」とは、例えば商品等のFAQページのことを指しており、問い合わせ数の減少を図ることで社員の負担を減らし、業務改善に寄与することを目的としているサイトです。
こうしたサイトで見るべき項目は、「閲覧数」や「PV数」、あるいは「滞在時間」です。これらの項目を見ていき、どれだけのユーザーが情報を求めているのかをチェックするのです。
ただし一つ注意をしておきたいのは、こうしたサイトは通常のサイトとは数値が持つ意味が反対の場合があるということです。例えば「PVが多い」ことは「それだけ商品・サービスに不明な点があるユーザーが多い」と、「滞在時間が長い」ことは「その分解決に時間がかかっている」とも読み取ることができます。そのため、これらの数値が高いときは、FAQサイトのあり方、あるいは商品やサービスのあり方そのものを見直していくことを検討したほうが良いでしょう。
目的4:Webサイトを通して商品・サービスを販売する場合
商品やサービスを販売することを目的にしているサイトの場合、まず見るべき項目は「販売数」です。それと同時に、こうしたサイトは同じユーザーになんども買ってもらうことも重要なことなので、「訪問者数」と「リピーター数」、そしてそこから割り出すことができる「リピート率」の推移にも目を見張っていきましょう。
ページの役割ごとに見るべき項目を変えることも
ここまではサイトの目的別に見るべき解析項目を紹介してきましたが、ページの役割ごとに見るべき項目を考えるということもできます。
そもそもWebサイト上のページは必ず2つに分類することができます。1つはTOPページや製品一覧ページなどの「インデックスページ」です。インデックスページはそれ単体では目的を達成することができず、必ず下層ページへと誘導をしなくてはなりません。つまり、滞在時間が短く、直帰率や離脱率が低いと、ポジティブな評価に値するのです。
もう1つは、インデックスページから誘導される下層ページ、つまり「目的先のページ」です。このページでは、文章や写真、動画などのコンテンツをじっくりと見てもらうことを望むため、滞在時間が長いことが評価に値します。
このように、ページの役割ごとにアクセス解析の方法を変えていくことも1つの手段と言えるでしょう。
毎日のチェックを続け、アクセス解析に慣れていこう
このようにWebサイトの目的から、あるいはページの役割から考え、それによって解析ツールの使い方を決めていくと、見るべき項目が絞られてきます。項目を絞れば「この数値だけを見るのであれば、毎日の確認も苦にならない」と感じることができるのではないでしょうか。
ただしここまでに記載してきたことは、あくまでも「最低限」のものであるとも言えます。例えば認知向上を目的としたサイトでは「訪問者数」や「閲覧数」が重要と記しましたが、サイトと認知向上の関係をより詳しく見ていくためには、ユーザーがどこから来たのかを見るために「流入先」や「検索キーワード」を見ていくことや、「一人当たりの閲覧ページ数」や「滞在時間」などを見ていくことも効果的です。
このように、アクセス解析に慣れてきたらより多くの項目や、いくつかの項目を掛け合わせてその関係性を見ていくことで、より精度の高い分析ができるようになるのです。まずは最低限の項目を日々チェックしていき、だんだんとステップを踏んでいくようにしましょう。
アリウープでは、多くのお客様のアクセス解析支援を行い、より成果が出るWebサイトに成長させてきた実績がありますので、是非気になる方はお問い合わせくださいませ!
また、GA4移行したものの設定ができているか気になる、しっかり運用したいけどどうしたらいいかわからない…という方は以下ホワイトペーパーを活用ください。GA4で正しい分析・解析を行い、PDCAを効果的に回して、サイトを成長させる方法をお伝えいたします!
↓ダウンロードはこちら